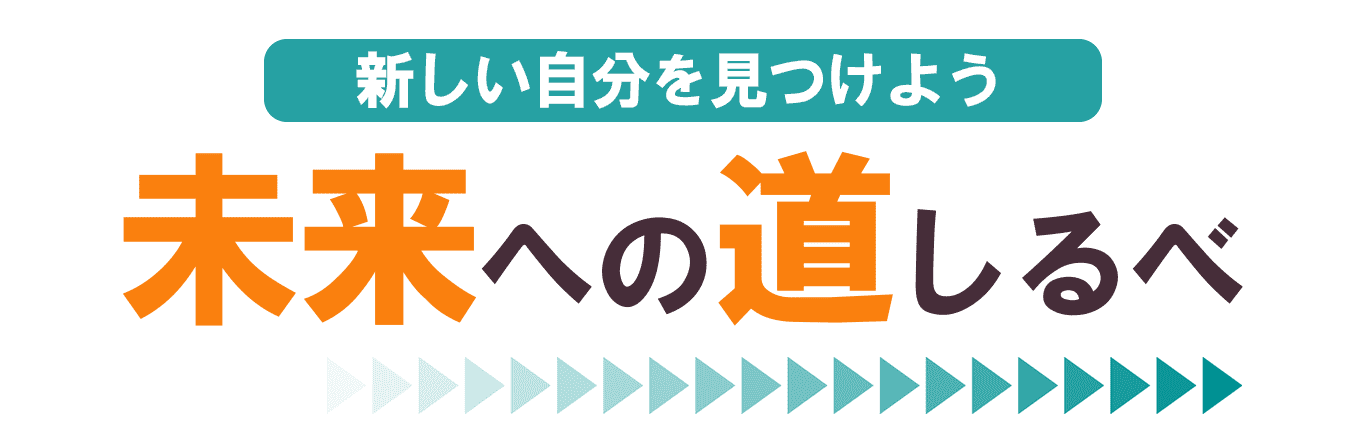将来の方向性を考えることにプレッシャーを感じたことはありませんか?「自分に合った仕事ってなんだろう」「このまま進んでいて本当にいいのだろうか」など、キャリアについて考えるとき、多くの人が不安や迷いに直面します。
しかし、必ずしも具体的なゴールが最初から必要というわけではありません。大切なのは、自分が納得できる生き方を見つけるための地図を描くことです。
この記事では、キャリアプランを考えるうえでの誤解や基本の視点、将来の見通しを立てるためのステップなど、迷わないための思考法を丁寧に解説します。
キャリアプランを考えるうえで陥りがちな3つの誤解

キャリアについて考えるとき、多くの人が無意識のうちに抱えてしまう思い込みがあります。それが原因で、選択肢を狭めたり、自分にプレッシャーをかけすぎたりしてしまうことも。まずはその「誤解」に気づくことが、柔軟な思考の第一歩です。
「最初に決めた道を変えてはいけない」という思い込み
キャリアを一度決めたら、その道を突き進まなければならないと考える人は少なくありません。特に新卒で入社する企業が“最初の正解”とされがちで、「やり直しは許されない」「ブレたら負け」といった思考に縛られてしまうことがあります。
しかし、実際には多くの人が途中で見直し、方向を変えたり、違う業種や職種に挑戦したりしています。時代の変化や自分の成長に伴って価値観は変わるもの。むしろ、変化に柔軟であることのほうが、長い人生を充実させるうえで大切です。
「今の選択が絶対的な答えでなくてもいい」と思えれば、目の前の判断にも余白が生まれます。軌道修正を重ねながら、自分にとって心地よい道を探していく“継続的なプロセス”なのです。
「やりたいこと」を無理に見つけようとする焦り
キャリアプランを立てる際、「自分のやりたいことが分からない」と悩む人は多くいます。そうしたときに、「明確な目標がないといけない」「夢や情熱がなければだめだ」と思い込み、無理に“それっぽい目標”を設定しようとするケースも見られます。
しかし、やりたいことは、頭でひねり出すものではなく、経験の中から少しずつ輪郭が見えてくるものです。無理に決めた目標は、自分の内側とずれていて、途中で息切れしてしまうこともあります。
まずは「やってみたいと感じたことに取り組んでみる」「少しでも興味が湧いたものを深掘りしてみる」といった小さな行動から始めることが、結果的に“本当にやりたいこと”へとつながる可能性を高めます。
キャリアとは、最初から完成された未来像を描くことではなく、「仮の方向性を持ちながら試行錯誤を重ねていく」動的なプロセスです。焦らず、経験のなかで見つけていくという姿勢こそが、本質的に欠かせません。
「安定した仕事=幸せ」という短絡的な判断
「安定しているからこの仕事を選んだ」「将来の安心のために職業を決めた」という選択も、多くの人が通る道です。もちろん、経済的な安定や職場環境の良さを重視することは悪いことではありません。
しかし、安定という言葉にばかり引っ張られてしまうと、本当に自分が望んでいる働き方や生き方を見落としてしまう可能性があります。たとえば、「仕事はつまらないけれど生活のために仕方ない」と感じながら働き続けると、やがて心のエネルギーが枯れてしまうこともあります。
本当の意味での「安定」とは、自分にとって心地よい働き方を長く続けられること。外的な条件だけでなく、「自分が納得できるか」「長期的に幸せを感じられるか」という内面の充実度にも目を向ける必要があります。
“安定=幸せ”という思い込みを一度ほどいて、自分が本当に望むことに目を向けてみる。そうすることで、自分に合った選択肢が広がっていきます。
キャリアプランの基本となる3つの視点

「何を軸に判断すればいいのか分からない」と感じることも多いでしょう。その際に役立つのが、“Will・Can・Must”という3つの視点です。
これは、自分のキャリアを内面と外面の両面から捉え、方向性を見つけるための思考フレームです。理想論に偏らず、現実的な視点も取り入れながら、自分なりの選択をするための土台になります。
Willは自分がやりたいこと(価値観)
Willとは、「自分がやりたい」「こうなりたい」と感じる内面的な動機や価値観を指します。これは単に「好きなこと」という表面的な話ではなく、「何にやりがいを感じるのか」「どんなことに意味を見出すのか」といった深い部分を見つめることが求められます。
たとえば、人と関わることで充実感を覚える人もいれば、成果を数値で見ることにやりがいを感じる人もいます。あるいは、「安定性」や「自由度」を大切にする価値観も、Willの一部です。
Willを知るには、過去の経験を振り返って「心が動いた瞬間」を掘り下げてみることが効果的です。何に感動し、何に怒りを感じたのか。そこに、自分が大切にしている軸が見つかる可能性があります。
自分の価値観を明確にするためには、まず自己分析の方法を知ることが役立ちます。自己分析の基本を解説した記事も参考にしてみてください。
Canは自分ができること(経験・強み)
Canは、これまでに身につけてきたスキルや知識、得意なこと、実績など、「自分ができること」を表します。これは自信の裏づけにもなり、現実的にどんな仕事に適性があるのかを判断する材料となります。
「自分には強みなんてない」と感じる人も少なくありませんが、過去に達成してきたことや人から褒められた経験、周囲から頼られたことを振り返ることで、多くのヒントが得られます。どんなに小さな経験でも、そこに活かせる要素が隠れています。
また、Canは変化していくものでもあります。今は未経験でも、学んで伸ばしていけるスキルも多いため、「将来的にできるようになりたいこと」も視野に入れておくと、柔軟にキャリアの幅を広げることができます。
Mustは社会や組織から求められること(市場価値)
Mustとは、社会や企業が求めていること、つまり「自分が社会にどう貢献できるか」という外部視点です。どれだけ自分に意欲と能力があっても、それが必要とされていなければ仕事として成立しにくいため、市場のニーズや業界の動向も押さえておく必要があります。
たとえば、ITや医療、環境関連など、今後も需要が高まる分野はMustの領域に含まれます。反対に、縮小傾向にある業界に興味がある場合は、どのような形で自分の価値を提供できるかを考えておくことが重要です。
WillやCanに偏りすぎると理想論に傾き、Mustばかりを優先すると自己犠牲的な選択になりがちです。3つのバランスを意識しながら、自分なりの軸を構築していくことが、自信のある選択につながります。
キャリアの方向性を描くための思考法

キャリアプランを考えるためには、「まずどこから手をつけたらいいか分からない」と戸惑うこともあるかもしれません。ここでは、具体的なステップとして、思考の流れを3つに分けて整理していきます。無理にすべて完璧にしようとせず、ひとつずつ丁寧に考えていくことがポイントです。
自分の過去を振り返る(経験・達成感・挫折)
最初に取り組みたいのは、これまでの人生の中で印象に残っている出来事を振り返ることです。学生時代の経験、仕事の中で達成感を得た瞬間、あるいは失敗して悔しさを感じた場面など、自分の感情が大きく動いた瞬間を思い出してみてください。
なぜその出来事が印象に残っているのか、どんな力を発揮できたのか、どのような考え方で乗り越えたのかなどを掘り下げていくと、自分の価値観や強みのヒントが浮かび上がってきます。こうした経験の中に、「自分らしく働ける環境」や「本当に大切にしたいこと」の手がかりが隠れているのです。
このプロセスは時間がかかるかもしれませんが、焦らず少しずつ言葉にしていくことが大切です。紙に書き出す、信頼できる人に話してみるなど、自分に合った方法で過去を整理することで、将来に活かせる土台が固まります。
5年後・10年後をざっくり想像してみる
次に、自分の未来像を描いてみましょう。「5年後にどんな働き方をしていたいか」「10年後にどんな自分でありたいか」を、具体的でなくても構いませんので、思いつくままに想像してみてください。
ここで重要なのは、「肩書き」や「役職」を思い描くのではなく、「どんな日常を送りたいか」「どんな人たちと関わっていたいか」「仕事を通じてどんな価値を生み出したいか」といった感覚的な問いに目を向けることです。
たとえば、「自分の意見を尊重してくれる環境で働いていたい」「誰かの成長を支える役割に就いていたい」などのイメージは、キャリア選択における道しるべになります。明確なゴールが見えなくても、方向性の“仮置き”ができるだけで、次に進むべき選択肢が見えやすくなります。
未来を思い描くことで、現在とのギャップが浮き彫りになりますが、そのギャップこそが「今、自分が何をすべきか」を考える材料になります。
将来像が見えてくると、志望動機の言葉にも深みが生まれます。志望動機が書けないときの考え方をあわせて読むと理解が深まります。
実現のために「今できること」を洗い出す
理想や方向性が見えてきたら、最後に「今の自分ができること」「すぐに始められる小さな行動」を洗い出してみましょう。大きな目標に対して、いきなり完璧な計画を立てようとすると挫折しやすくなるため、まずは一歩ずつ前に進めるような実践的な行動を意識することが大切です。
たとえば、興味のある分野の本を読んでみる、セミナーや説明会に参加する、SNSで業界の情報を収集する、あるいは信頼できる人に相談してみる、といった行動でも構いません。小さな行動を積み重ねることで、キャリアの輪郭が徐々に明確になっていきます。
このステップでは、「完璧な一歩」よりも、「無理なく続けられる一歩」を選ぶことが成功の鍵です。実践を通じてフィードバックを得ることで、自分の選択や思考が磨かれ、方向性が自然と定まっていきます。
キャリアプランに“迷い”はつきもの。定期的な見直しを

キャリアプランは、一度決めたらそれで終わりではありません。むしろ、「迷って当然」「変わって当然」と考えることが、柔軟性を持たせるためには重要です。人生のステージが変われば、価値観も、優先順位も、できることも変化します。その都度見直しをしながら、自分の今の状態に合った形に更新していくことが大切です。
たとえば、入社当初は「専門スキルを極めたい」と考えていても、数年経って「マネジメントに興味が出てきた」と気づくこともあるでしょう。その変化は成長の証でもあり、恐れるべきものではありません。
迷いが生じたときこそ、自分の原点に立ち返る好機でもあります。なぜその道を選んだのか、何を目指していたのか。迷いは、自分を見直すための大切なタイミングなのです。
定期的に自分のキャリアを棚卸しし、「今、何を感じているか」「これからどうしたいか」を確認する習慣を持つことで、道に迷ったときにもブレずに再出発できる力が養われます。
入社を控えて不安を感じる方は、不安を和らげる心構えをまとめた記事もぜひ読んでみてください。
おわりに
キャリアを考えるというのは、自分の生き方そのものを見つめることでもあります。仕事だけに限らず、「どんな人生を送りたいか」「どんな価値を大切にしたいか」といった視点があってこそ、本当に納得できるプランを描くことができるのです。
大切なのは、他人と比べて答えを探すことではなく、「自分にとっての正解」を時間をかけて見つけていく姿勢です。そして、その正解は一度きりではなく、何度でも更新していいもの。むしろ、更新していくことこそが、キャリアを豊かにしていく秘訣です。
焦る必要はありません。完璧な未来像を持っていなくても、今の自分にできることから始めてみれば、それが確かな一歩になります。あなたが自分の価値を活かせる場所を見つけられるよう、このガイドが少しでも参考になれば幸いです。