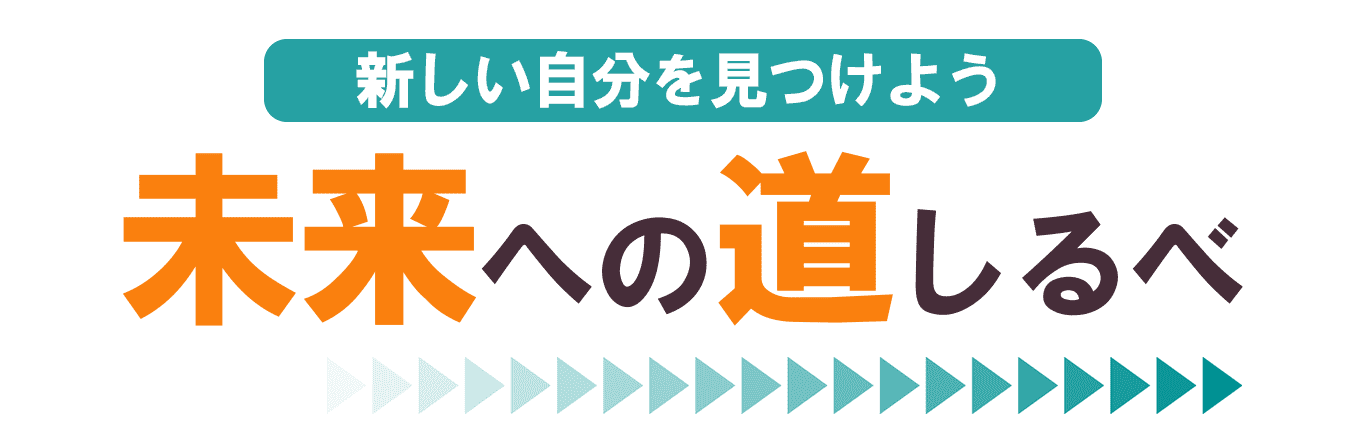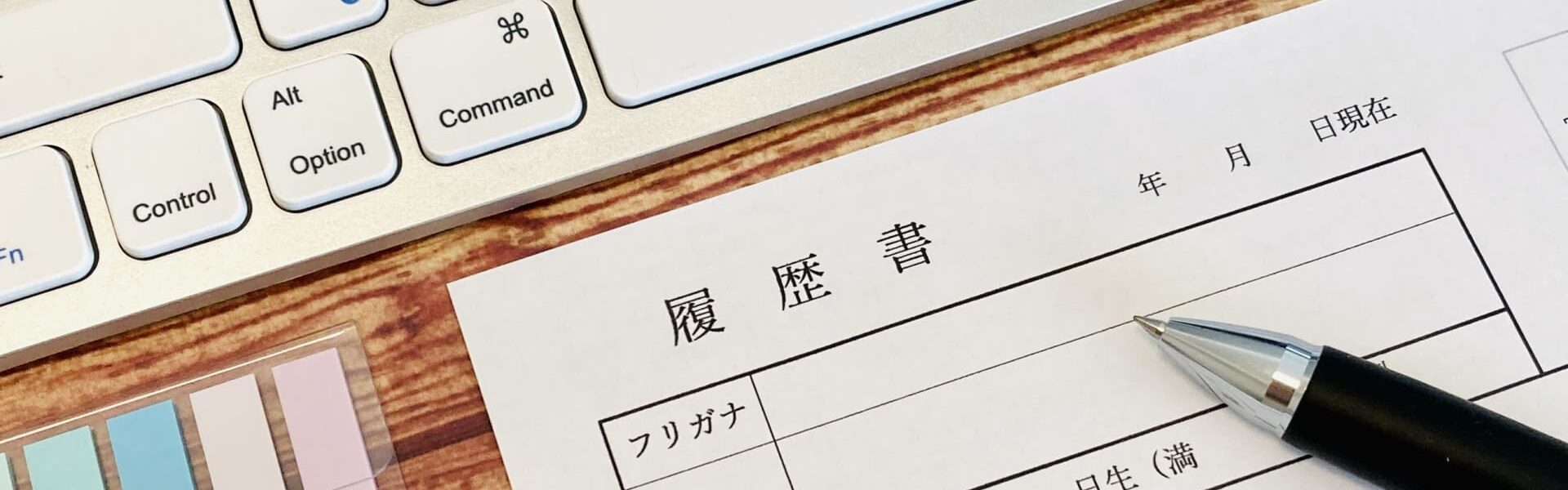就職活動や転職活動で必ず求められる「志望動機」。書類を開いたとたん、何を書けばよいかわからず、手が止まってしまった経験はありませんか。頭の中では「この会社に入りたい」と思っていても、いざ文章にしようとすると言葉が浮かばない。そのまま時間だけが過ぎ、焦りが募っていく――。そんな状態に陥ってしまう人は、実はとても多いのです。
本記事では、志望動機が書けない理由をひもときながら、自分の気持ちを整理し、「納得できる志望動機」にまとめるための考え方と書き方を丁寧に解説します。表面的な例文のコピペではなく、自分の経験や価値観を軸にした“伝わる志望動機”を見つけるための一歩としてお読みください。
志望動機が書けない原因

「気持ちはあるのに、うまく言葉にならない」。そう感じるとき、実は頭の中で「本心」と「こうあるべき」がぶつかり合っていることがあります。「この会社の雰囲気が好き」という素直な気持ちがあるのに、「ちゃんとした理由を書かないと評価されない」という思考が、それを否定してしまうのです。
その結果、本音から遠ざかった無難な言葉ばかりが浮かび、どれも自分の言葉としてしっくりこない。そんな状態では、納得できる志望動機にはなりません。
まず大切なのは、「評価されることよりも、自分が納得できる理由を見つけること」です。自分自身が心から「これだ」と思える動機でなければ、たとえ文章が整っていても、読み手には何も伝わりません。感情を抑えこまず、「なぜそう思ったのか」「どう感じたのか」を言葉にする練習から始めてみてください。
魅力的な志望動機を書く方法

多くの人は、「論理的な志望動機を書かなければ」と構えすぎてしまい、自分の本当の気持ちを押し殺してしまいます。しかし、「なんとなくこの会社が好き」「なぜか興味がある」という直感も、立派な出発点です。重要なのは、その理由を自分の言葉で掘り下げていくことです。
たとえば、「なんとなく安心感がある」と感じたとしたら、「なぜ安心感を覚えたのか?」と問いかけてみましょう。「社員のインタビューに親しみがあった」「社風が自分の価値観と似ている気がした」など、具体的な言葉が少しずつ見えてきます。
言語化できるようになるまでに時間がかかっても構いません。書き出すうちに、「自分が大切にしているもの」「働く上で欠かせない条件」「過去の経験とのつながり」などが、少しずつ浮かび上がってくるはずです。
志望動機は「相手に合わせるもの」ではなく「自分の軸を伝えるもの」
インターネット上には無数の志望動機例文が存在します。たしかに、型を知ることは参考になります。ただし、そのまま真似をしても、あなた自身の思いは伝わりません。採用担当者が本当に知りたいのは、「なぜこの会社を選んだのか」というあなたの考え方と、その理由の“深さ”です。
たとえば、「成長できる環境に惹かれました」という一文。表面的には魅力的に見えるかもしれませんが、これだけでは他の人と差がつきません。ここに、自分の経験や価値観が伴ってはじめて、説得力が生まれます。
「私は学生時代、部活動でうまくいかなかった経験を通じて、地道に積み重ねる姿勢の大切さを学びました。だからこそ、貴社の『努力の積み重ねを評価する文化』に強く共感しました」
このように、自分の過去の経験がその企業とどうつながっているかを具体的に示すことで、読み手の印象に残る志望動機になります。
自己理解やキャリア設計を深めたい方は、厚生労働省のキャリア支援ページも参考になります。
企業研究や業界理解は、あくまで「裏づけ」である
よく「企業研究を徹底しよう」と言われますが、それは「企業に合わせて書くため」ではありません。自分の気持ちや考えを裏づけるための材料として企業を深く知るのです。
たとえば、あなたが「人の感情に寄り添える仕事がしたい」と思っていたとします。そのとき、「この会社が提供するサービスが、利用者の不安にどう向き合っているか」を知っていれば、「自分の価値観と企業の姿勢が合っている」と明確に伝えられるようになります。
企業研究とは、企業の顔色をうかがうのではなく、「この企業と自分は本当に相性がよいのか」を確かめる作業でもあるのです。
「なぜそう感じたのか」を掘り下げるには、自己分析が欠かせません。自己分析のやり方をチェックして、志望動機づくりに役立てましょう。
今すぐ書きたい人へ!志望動機の基本構成とテンプレート

志望動機を書き出すために、具体的な型や書き出しの工夫を知っておきたいという方もいるかもしれません。実際、どんなに考え方が整理されていても、いざ文章として形にしようとすると、どう始めたらよいのかわからなくなることは珍しくありません。
そんなときは、基本の構成を一つの「流れ」として捉えてみてください。たとえば、最初に志望する理由を簡潔に述べ、そこからその思いが生まれた背景や、自分の経験と重なる部分へと話を展開していきます。次に、その企業でなければならない理由を言語化し、最後に「その環境でどう働きたいか」「どのように貢献したいか」という未来の姿を添える。こうした順番を意識することで、言葉にまとまりが出やすくなります。
文章の出だしに迷ったときは、自分の経験を起点にして始めてみると自然です。「大学時代、〇〇の活動を通じて△△を学びました」や「〇〇に取り組んできた中で、人と関わることの大切さを実感しました」といった書き方であれば、あなたの背景が伝わりやすくなります。また、「御社の〇〇という姿勢に共感した」など、自分の考えと企業の価値観を結びつける文章に続けると、より一貫した印象を与えることができます。
応用編!文章に深みを持たせるには?
文章に深みを持たせたいときは、自分に問いかけるように掘り下げていく方法が効果的です。たとえば、「どんなときにやりがいを感じたか」「なぜそれが自分にとって大切だったのか」「その想いと企業の特徴がどう結びついたのか」という問いをひとつひとつ考えていくことで、表面的な志望動機ではなく、あなただけの“背景のある言葉”が見えてきます。
実際の構成に沿ってまとめた志望動機の例文
私が貴社を志望したのは、「一人ひとりの声を大切にする姿勢」に強く共感したからです。大学時代、地域の相談窓口でボランティアをしていた際、相手の話を丁寧に聞くことが信頼関係の第一歩になることを実感しました。貴社の事業内容と、そこで働く方々の姿勢が、自分の価値観と一致しており、「ここで働きたい」と自然に思うようになりました。将来は、相手に寄り添う提案ができる人材として貢献していきたいと考えています。
このように、自分の体験と企業の姿勢が自然につながっていれば、過剰に美しい言葉を使わなくても、相手の印象に残る志望動機になります。完璧な表現を目指すのではなく、「自分の言葉で書く」という姿勢を大切にしてみてください。文章の中にあなたの実感が宿れば、それだけで十分に魅力が伝わります。
おわりに
志望動機が書けないことを、マイナスに捉えなくても大丈夫です。言葉にならない時間は、気持ちを整理する大切な時間でもあります。焦らずに、自分の中の“本当の動機”を見つけようとする姿勢が、やがて自信につながっていきます。
例文をなぞるのではなく、あなたの過去、感じたこと、考え方をベースにした言葉こそが、採用担当者の心を動かします。正解を探すのではなく、あなたにしか書けない言葉を探してください。
その結果、たとえ文章が完璧でなかったとしても、誠実な姿勢と自己理解の深さは、必ず相手に伝わります。自分の気持ちを言葉にする過程は、就職や転職のためだけでなく、これから社会で働くうえでの大きな土台にもなっていきます。
どんな一文からでも構いません。まずは、自分の中の「なぜ、この会社なのか」という問いに、正直に向き合うことから始めてみてください。